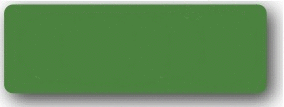-Chuck is very good-
ハイファイ堂メールマガジン第691号 日本橋店
ハイファイ堂メールマガジン第691号 日本橋店
|
Red Necker's Rock'n'roll -Chuck is very good- 日本橋店 渡辺 正 「鳥肌音楽 Chicken Skin Music」というブログで3月18日他界したロックン・ロールの父=チャック・ベリーへの追悼として、かなり昔のキネマ旬報での小林信彦と大瀧詠一対談による”ミュージシャン必見の「バック・トゥ・ザ・フューチャー」”という記事が取り上げられていた。 http://ameblo.jp/sugarmountain/entry-12257707448.html 「バック・トゥ・ザ・フューチャー」は大好きな映画のひとつなのだけれど、ロックの歴史が凝縮されていると評判のダンスパーティーのシーンがどうにも釈然とせず、観終えてからどうにもモヤモヤした気持ちになった昔の記憶が久々に蘇った。 ということで、今回のお題は黒人サイドから見たロックンロールの誕生とチャック・ベリーについての自分なりの考察をしてみます。 独り善がりの駄文に暫しのお付き合いを。。。 |
|

|
|
|
画像出典:ウィキペディア |
|
|
-That Lucky Old Sun- 17世紀から19世紀までに、アフリカ大陸から北米に連れてこられた黒人の数は1,200万人を越えると言われている。 ”黒人たちが奴隷にされた他のどの国においても、合衆国におけるほど、アフリカ文化が破壊されたところはなかった。今日においても、南アフリカやカリブ海諸島においては、奴隷船によってやってきたアフリカの宗教、音楽、言語が、あいかわらず存在している。合衆国の黒人たちの間では、アフリカの破片だけしか残っていない。”・・・(ジュリアス・レスター著『奴隷とは』/岩波新書) 北米の農園主らは、黒人奴隷が結束して反乱することを恐れて、同じ部族同士はバラバラにされ、言語や文字の教育はおろか、アフリカ固有の楽器すら使用を認められず、徹底的に彼らの共通文化を消し去ろうとした。 そんな中、バラバラに分断されて、言葉も文化も自分の名前すらも奪われてしまった黒人奴隷たちが、最低限の人間らしい生活をするために、自発的にアメリカ英語を覚えた。会話ができると自然と口から歌がでる。リズミカルに声をかけ周囲がそれに呼応する、アフリカ固有のいわゆるコール&レスポンスによる素朴な歌だ。ヨイトマケの唄の「とーちゃんのためならエンヤコラ、かーちゃんのためならエンヤコラ、もひとつおまけにエンヤコラ」のような感じと言えば分かり易いかも知れない。過酷な労働への悲哀や仲間同士の鼓舞を歌ったものはワークソング、神に語りかけるように祈り歌ったのがスピリチュアルソングと呼ばれた。 彼らは英語を習得して、祈りの対象をアフリカの神々からキリスト教の神に置き換えて、歌うこと、踊ることで、自らのアイデンティティーを再び見出していった。 このシンプルな音楽こそが、後に世の中のポップミュージックシーンを席巻することになるブラックミュージックの原石なのである。 |
|
|
-Super Blues- 20世紀に入ると、ワークソングはブルースへ、スピリチュアルソングはゴスペルへと発展していく。地を這うブルースと天を舞うゴスペル、いずれも表裏一体で根っこにあるものは同じだ。その根っこにある黒人の魂と言うべきものを抽出して、流行歌のフィールドで提示した音楽がR&Bでありソウルミュージックである。 2009年公開の「キャデラック・レコード 音楽でアメリカを変えた人々の物語」はシカゴのブルース専門レーベルのチェスレコードを描いたミュージカル仕立ての伝記映画だ。レーベルオーナーのレナード・チェスとブルースマンのマディ・ウォーターズの二人を軸にリトル・ウォルターやエタ・ジェイムスが絡む。そこにはミシシッピの広大な綿花畑で歌われていた塩辛いブルースが、ギターにアンプを通すことで革新的音楽「ロックンロール」に変わって行く様が克明に描かれている。 1940年代末期。ミシシッピの一農夫であったマディ・ウォーターズは音楽に夢を託して大都会シカゴにやってきた。そこで最初に出くわすのが、路上でハーモニカを演奏するリトル・ウォルターの姿。群がる聴衆の前でウォルターは手にハーモニカとマイクを握り、小型のギターアンプを通して音を出していた。アンプのボリュームを目一杯上げたその音はひしゃげて潰れまくっている。マディはその荒々しい音色に痺れ、インスピレーションを受け、自身の演奏スタイルをアコースティックギターからエレキギターに変えることを決める。 話がそれてしまうが、聞いてほしい。西洋楽器の起源はアフリカである。曖昧な音程やノイズを発する原始的なアフリカの民族楽器がヨーロッパに渡って、改良されクリーンなトーンと明瞭な音程のピアノや弦楽器や管楽器になる。黒人たちはクリーンなトーンの西洋楽器を、アンプで敢えて歪ませることで、アフリカの民族楽器のような音色を戻して、より深く複雑な感情を音楽で表そうとした。これを音楽評論家の中村とうよう氏は楽器の先祖帰りと表現した。 本来、より多くの聴衆に音を届ける為に考えられたアンプリファイドという技術も、黒人ミュージシャンが使うと、それまで全く考えの及ばないベクトルに向かい出す。西洋楽器の音響工学的に洗練された音色は、物凄い技巧を駆使して演奏することで、絶大な歓喜や深い悲しみは表現出来るかもしれないが、黒人音楽特有(後のポピュラーソングにも言える)の日常の微妙な機微やニュアンスを表現するには物足りない。ギターのボトルネック奏法も同じ発想で、酒瓶の首の部分を弦に当てスライドさせることで音階を曖昧にしたりノイズや不協和音をつくりだすことで黒人音楽の根っこの部分を表現した。 1619年、最初に黒人達が北米に上陸したとの記録があるそうだが、以来彼らの歴史は、そこにあるものを流用して、奪い取られたアイデンティティを再構築する歴史だった。そして2世紀の時を経た1950年代の中頃、アンプリファイドという技術を持ってして、全く新しいアフリカンミュージックを雪の降る大都会の片隅に響き渡らせることになる。 |
|

|
 |

|
-2120 South Michigan Avenue 1- アコースティックギターをエレキギターに持ち替えたマディ・ウォーターズは代表作とも言える「I'm Your Hoochie Coochie Man」をチェスレコードよりリリース。 ビリビリに歪みながら大きくうねるマディのブルースは黒人たちから絶大な支持を得た。マディは一躍チェスレコードの看板アーティストとなる。早い時期での電気楽器導入など、固定観念にとらわれない発想と先見性のあるマディはレーベルオーナーのレナード・チェスの信頼を勝ち取り、レナード・チェスの右腕として経営手腕も発揮するようになる。 黒人マーケット中心のチェスレコードがより大きなマーケットに参入するためにマディは1955年にチャック・ベリーをチェスに引き入れる。チャックのギタープレイの基本はマディのようなエレクトリックなブルースである。そこにスイングジャズ、ブギウギや白人のカントリーミュージックなどの要素を盛り込んだものだ。そして、チャックを決定付けたのが、グッと腰を落としてアヒルのようなヨチヨチ歩きでギターを弾く「ダックウォーク」のパフォーマンス。マディのブルースの延長線上にありながら、マディにはないポップで軽やかなスイング感をチャックは持っていた。 画像出典:ウィキペディア |
|
-Moondog Coronation Ball- ブルースでありながらブルースには無いフィーリング。これをアラン・フリードは「ロックンロール」と定義した。 1950年代から1960年代のアメリカは繁栄を極め、空前のベビーブームによるティーンエイジの文化が開花した時代でもあった。音楽もティーンエイジに向けて、いかに刺激に満ちた音を届けるかに各レコード会社が重点を置いていくようになった。 そんな時代の気分を巧みにすくい取り、良識ある大人達から反感を買いながらも、ラジオDJのアラン・フリードは、讃美歌でもカントリーソングでもない跳ねの強い黒人音楽を「ロックンロール」と叫びながらプレイして喝采を浴びた。 黒人のアイデンティティの発露であったブルースやR&Bが、白人ティーンエイジャーを狂喜乱舞させた時に、その音楽は「ロックンロール」と呼び名が変わった。 画像出典:ウィキペディア |

|

|
-2120 South Michigan Avenue 2- 『南ミシガン通り2120番地は俺たちにとって聖地だった。シカゴのチェスレコードの所在地だ』ローリングストーンズのギター担当キース・リチャードは自伝でこう語っている。1963年、彼らは聖地チェスレコードを訪れ、レコーディングを行った。 キースはダートフォート駅のホームでボーカル担当のミック・ジャガーと出会い、ミックが脇に抱えていた3枚のチェスレコードのLPを見つけて、意気投合しローリング・ストーンズを結成した。その3枚のLPこそがマディ・ウォーターズとチャック・ベリーそしてハウリン・ウルフだった。ちなみにローリング・ストーンはマディ・ウォーターズの曲名である。 アラン・フリードの蒔いたロックンロールの種は海を隔てたロンドンの地でも芽を出した。 画像出典:BOOGIE WOOGIE FLU |

|
|
|
画像出典:BOOGIE WOOGIE FLU |
|
|
-Truck Drivin' Boogie- メンフィスでトラックドライバーをしていたエルビス・プレスリーは、まるで黒人のように歌い踊って、スターダムを駆け上がっていった。ブロンドの髪を、黒人のように黒く染めて、ブルースマンのように黒髪をポマードで後ろに撫で付けてクールを装っていた。 バディ・ホリーは、黒人エンターテイメントの殿堂アポロシアターに白人アーティストとして初めて出演。情報の少ない当時、プロモーターはバディ・ホリーの演唱をてっきり黒人と勘違いしたそうだ。白人と分かり狼狽する劇場関係者をよそに、バディ・ホリーのロックンロールは黒人観衆のやんやの拍手喝采を浴びた。 刺激を求めるティーンエイジャーにとってのクールは、ビートの効いた黒人音楽と、黒人のように振る舞うことだった。 |
|
|
-our Rock'n'roll thing- ”「バック・トゥ・ザ・フューチャー」(1985年)において、1955年にタイムスリップした主人公のマーティ・マクフライが、指を負傷したマーヴィン・ベリーというギタリストの代理としてダンスパーティのバンドでギターを演奏し、アンコールでこの曲を演奏するシーンがある。映画の設定上ではマーヴィンはチャックの従兄弟であり、主人公の演奏中に「新しい音楽を探していた」というチャックに電話をかけ、受話器越しに演奏を聴かせている。つまりチャック・ベリーは、未来からやってきたマーティの演奏を聴いてこの曲を着想した、というタイム・パラドックスになっている。”(ウィキペディア「ジョニー・B・グッド」より) https://ja.wikipedia.org/wiki/ジョニー・B.グッド ”小林信彦:「ジョニー・B・グッド」は、もう、あの時代には作られていたんですか。 大瀧:55年はまだないです。だけど58年の曲(註:58年に全米8位)ですから、時代設定としてはいいわけです。チャック・ベリーはあれにインスパイアされて、自分のスタイルを確立したということですからね(笑)”(ミュージシャン必見の「バック・トゥ・ザ・フューチャー」/『映画に連れてって 小林信彦対談集』キネマ旬報社) ここが違和感というか釈然としない部分なのである。2世紀という長い年月をかけて、北米の黒人たちがたどり着いたブルースやゴスペルと呼ばれる音楽。そこから派生したR&B。R&Bはカントリーミュージックなどとも異種勾配しながら白人聴衆を獲得して「ロックンロール」へと変わっていく。そのR&B〜「ロックンロール」の大きな渦のど真ん中に居たのがチャック・ベリーだろう。ここでは触れないけれど、欧米のポップスはほぼ全て黒人音楽からヒントを得てきたわけだ。 「ジョニー・B・グッド」演奏の前が、ドゥーワップの名曲「アース・エンジェル」。一番有名なクルー・カッツという白人グループのバージョンではなく、オリジネイターの黒人グループ、ペンギンズに忠実なバージョンだったのがシブかっただけに、「ジョニー・B・グッド」の件はあまりにもデリカシーに欠けて、残念でならない。。。 そういえば、1963年リリースのビーチ・ボーイズ「サーフィン・U.S.A.」は1958年全米チャート2位のチャック・ベリー「スウィート・リトル・シックスティーン」の改作であり、チャックの訴訟によりビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソン作曲からチャック・ベリー/ブライアン・ウィルソン共作へとクレジットが改められたことは有名な話である。偶然ラジオから流れる「サーフィン・U.S.A.」を耳にしたチャックは、驚きひどく憤慨したという。このエピソードは前出の「キャデラック・レコード」「ドリームガールズ」の映画でも白人中心の音楽産業による搾取の象徴として取り上げられている。 |
|
|
-Sweet Little Rock and Roller- 良くも悪くも「ロックンロール」は、黒人コミュニティの枠をぶち破り、より開かれた大きな社会に打って出ることで、化学変化を起こし火花を散らし、雪だるま式に巨大化していった。 音楽は決して選ばれた天才と呼ばれる人が突然閃いて作ったものではない。世の中の流れの中で多くの人たちの営みや偶発的な出来事が重なって、大きな音楽の渦が巻き上がるのだと思っているし、ひとりの天才ミュージシャンと同様に、その大きな渦が重要だと思っている。 「ロックンロール」の大きな渦の中で、誰よりも腰を低くかがめてギターをかき鳴らしていたのがチャック・ベリーだったんだろう。 |
|
大須本店
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-14-37 (052)249-2600
秋葉原店
〒101-0021 東京都千代田区外神田5-3-12清和ビル1F 3F (03)5818-4751
日本橋店
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-6-9 (06)4396-7611
福岡店
〒810-0041 福岡市中央区大名2-6-40 文學の森ビル1F (092)724-3681
-

-

- English
- 会社案内・振込先
- お問い合せ受付け
- インターネット参加
- オーディオ買取
- メルマガバックナンバー
- メルマガ登録・解除
-
特定商取引法及び
古物営業法による表記 - ハイファイ堂みせますカム!
- 入荷案内登録
- ポイント会員特典について
- 修理規定
- 送料について
- 返品ポリシー
- プライバシーポリシー
-
過去情報データベース
- 大須本店
-
2025-11-28 歴史的銘ユニットGOODMANS AXIOM80が入荷しました!レスポンスが良く、透明感のある澄んだ高域が魅力的です。ご興味ある方ぜひお気軽にお問い合わせください。

- 福岡店
-
2025-12-12 福岡店の新着です。JBL S2600 が内外装綺麗にメンテナンスされ販売中です。ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。

- 商品部
-
2025-12-12 現在メンテナンス中のスピーカー達です!近々商品化されると思いますので是非ご検討ください!TANNOY Westminster Royal、TANNOY Autograph、TANNOY Rectangular

- 秋葉原店
-
2025-12-11 お店のフロントには目を惹くVIVID AUDIOが鎮座しております。奥にはMAGICOのS1などございます。店頭で試聴も可能ですので、お気軽にご来店下さい。

- 日本橋店
-
2025-12-12 JBLの46cmウーファー2240Hを2本搭載した巨大スーパーウーファー、4788Aが日本橋店に入荷しました。80Hz〜の深い低音が楽しめます。幅1.5m、重量は122kgあります。メンテナンス後にホームページに掲載します。

-

一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC規定に基づいて営業しております